本会は7月17日から18日の2日間、盛岡つなぎ温泉「ホテル紫苑」において、「令和7年度換地委員等実務研修会」を開催し、ほ場整備実施地区の換地委員や計画地区の推進委員、土地改良区の担当者など約80名が受講しました。
研修に先立ち、本会 菅野 章 参与兼換地部長が「今年度、国は6,500億円の土地改良予算を確保しましたが、岩手県では現在70地区と多くのほ場整備事業が進行中であり、ほ場整備の完了には約20年を要しています。この進捗の遅さが岩手県の課題となっています。農家の平均年齢は68歳であり、ほ場整備を始めたとしても、完了時には90歳近くになってしまいます。少しでも早く進めるために努力していますが、皆様もそのような状況の中で換地委員として取り組んでいることに感謝申し上げます。かつては各農家に農地をどこに換地するかが課題でしたが、現在は法人化が進み、集団で営農する形に変わっています。換地を巡る情勢も日々変化していることを、今日と明日皆さんにお話しし、これからの換地に取り組んでいただきたいと考えています。2日間の研修は長丁場となりますが、よろしくお願いいたします。」と挨拶しました。
1日目は「換地の流れについて」と題し、本会換地部換地課 大沼 朋也 課長補佐から、換地の主な流れや、換地委員の役割、換地設計基準や土地評価基準の例について講義しました。
次に「農業農村整備を巡る状況について」と題して、本会 菅野 章 参与兼換地部長から、食料・農業・農村基本法の基本理念や水土里ビジョンと地域計画の関係、土地改良予算の推移について講義しました。
次に「農業農村基本計画の概要について」と題して、岩手県農林水産部農村建設課の中村 愛彦 技術主幹兼農地整備担当課長から、基本法の改正のポイント、食料供給をめぐる情勢、食料安全保障について講義しました。
2日目は、「鍋割川ユニオンの取組み、歩み」と題して、農業生産法人鍋割川ユニオンの 及川 光孝 代表取締役による先進地事例の講演が行われました。コスト縮減への取組みや会社の経営スタンス、集落との関係など様々な取組み事例や法人の歩みについて紹介しました。
次に「農地中間管理事業の概要について」と題して、岩手県農業公社農地中間管理部農地集積課の 新田 和 主査が、事業の仕組みや主な内容、事務フローや事業のよくある質問Q&Aについて講義しました。
次に「所有者不明土地問題の解明に向けた実例について」と題して、花巻市農林部農政課地域農業推進室の 藤沼 一志 主査から、基盤整備事業における所有者不明土地管理制度の具体的な活用事例について講義し研修を終えました。
2日間を通し、活発な質疑があるなど、受講者は真剣な面持ちで受講していました。

【本会換地部換地課 大沼課長補佐】
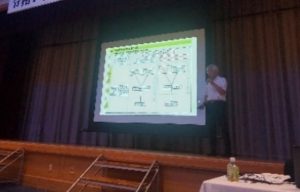
【本会 菅野参与兼換地部長】

【県農村建設課 中村技術主幹 兼農地整備担当課長】

【鍋割川ユニオン 及川代表取締役】

【岩手県農業公社農地集積課 新田主査】

【花巻市農林部農政課 藤沼 主査】

【受講の様子】
▼▼▼PDF版はこちらから▼▼▼
https://www.iwatochi.com/main/06/osirase/osirase1209.pdf
